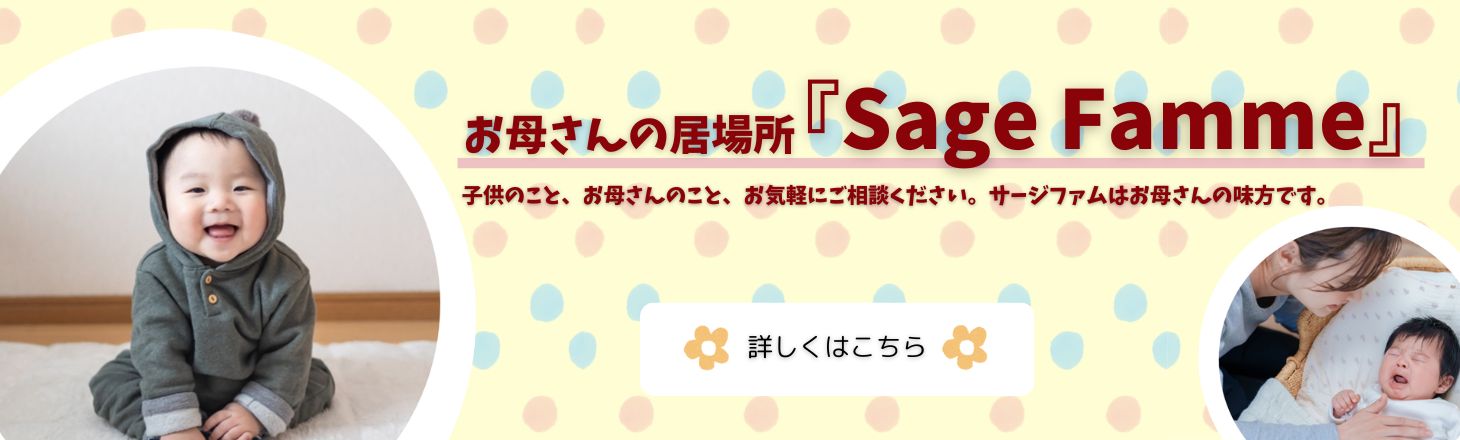高崎市の産後ケア・母親支援
お役立ち情報
産後うつのチェックリスト|気になる症状や予防のポイントも紹介

-
 この記事の監修
この記事の監修
髙津 三枝子(特定非営利活動法人 地域母親支援サージファム)・助産師免許
・群馬大学大学院医学系研究科博士前期課程修了
・群馬県内看護系大学、助産師学校非常勤講師
毎日子育てに奮闘し、心身ともに疲れを感じているお母さま方を少しでもお助けしたいという想いから、
特定非営利活動法人 地域母親支援サージファムを設立いたしました。以来、皆さまの育児が少しでも楽になるよう、日々努めております。
出産後は、心と体の両方が大きく変化し、今まで感じなかった不安や疲れが積み重なりやすくなります。
産後うつは、強い悲しみや不安、気力の低下などが続き、育児や日常生活に影響を与えることもある状態です。
早めに気付くことで回復に向かいやすくなるため、産後うつチェックで今の自分の心の状態を知ることは非常に大切です。
本記事では、産後うつの主な症状や原因、気持ちを軽くする工夫について分かりやすく紹介します。
目次
「産後うつ」ってどんな状態?

産後うつは、出産後に強い悲しみや不安、やる気の低下などが長く続く状態を言います。
妊娠中や産後は女性ホルモンの急激な変化や生活環境の変化が重なり、心が不安定になりやすい時期です。
出産後3日以内に見られる気分の落ち込みや涙もろさは「マタニティブルー」と呼ばれ、多くの場合2週間ほどで自然に落ち着きます。
一方で、産後うつは産後6〜8週ごろに始まることが多く、数週間から数カ月続くのが特徴です。
不眠や食欲不振、強い焦りや緊張感、赤ちゃんへの関心の低下などが見られ、育児や日常生活に影響することもあります。
産後うつの症状を放っておくと悪化し、まれに自分を傷つけてしまうほど深刻になることもあります。
【セルフチェックリスト】産後うつのサインとは
産後は心や体が大きく変化し、小さな違和感や気持ちの揺れが積み重なることがあります。
ここでは、産後うつのサインになり得るポイントを簡単にまとめました。
いくつか当てはまる場合は、無理せず早めに相談してみてください。
✅ 物事を楽しめない
→趣味や家族との時間に喜びを感じにくい
✅ 気分が落ち込み、涙もろくなる
→理由もなく沈んだ気持ちになり、涙が出やすい
✅ 不安や恐怖を感じやすい
→赤ちゃんや将来への過剰な心配が続いている
✅ 睡眠の質が下がる
→寝付きにくい、眠りが浅い、または寝過ぎる
✅ 赤ちゃんへの愛情が薄れる
→抱っこや授乳でも喜びや安心感が湧かない
✅ 自分を責める気持ちが強い
→小さな失敗でも「母親失格」と感じてしまう
✅ 食欲の変化がある
→食欲が落ちる、または食べ過ぎる
✅ 自分や赤ちゃんを傷つけたい気持ちが浮かぶ
→ネガティブな考えが浮かび、不安や罪悪感が強くなる
物事を楽しめない
今まで好きだった趣味や家族との時間、テレビや音楽などが、あまり心から楽しめなくなることがあります。
気持ちが沈み、興味や関心が薄れてしまうと、達成感や充実感を感じられない日が続きます。
笑顔や笑い声が減り、何となく一日が過ぎてしまう感覚が強くなることも。
単なる疲れではなく、物事を楽しめなくなる変化は、産後うつのサインのひとつと考えられています。
気分が落ち込み、涙もろくなる
特に理由が無くても、急に気分が沈み、涙が出やすくなることがあります。
ちょっとした出来事でも涙があふれ、感情のコントロールが難しく感じられることもあるかもしれません。
気分が落ち込む状態が続くと、人と話すことが億劫になり、家にこもりがちになることがあります。
涙もろさが日常生活に影響するほど強まっているときは、メンタルケアが必要かもしれません。
不安や恐怖を感じやすい
はっきりした理由がないのに、心配や不安が続いたり、ふいに強い恐怖感に襲われたりすることがあります。
赤ちゃんの体調や将来に対して過剰に不安を抱くことも多く、その思いが頭から離れなくなることもあります。
安心できる状況でも気持ちが落ち着かず、常に緊張しているような感覚が続くときは、心が疲れているサインかもしれません。
睡眠の質が下がる
夜間授乳や赤ちゃんの泣き声で眠れないだけでなく、静かな環境でもなかなか寝付けなかったり、眠りが浅かったりすることがあります。逆に、長時間眠ってしまうこともあります。
十分な睡眠がとれないと、日中の集中力や体力が低下し、気持ちの浮き沈みも大きくなります。
睡眠の質が長く落ちていると、心身の回復が難しくなりやすくなるため、要注意のサインです。
赤ちゃんへの関心や愛情が薄れる
赤ちゃんを見ても以前のような愛おしさを感じられず、日々のお世話を「やらなければならないこと」として捉えてしまうことがあります。
抱っこや授乳をしても喜びや安心感が湧かず、距離を置きたくなることもあるかもしれません。
必要な育児に取り組みながらも心がついてこない状態が続くと、罪悪感や自分を責める気持ちが強まりやすくなります。
自分を責める気持ちが強い
育児や家事で上手くいかないことがあると、必要以上に自分を責めてしまうことがあります。
「母親失格かもしれない」と感じたり、自分の価値を低く見てしまうことも考えられます。
客観的には十分に頑張っていても、自己否定の気持ちは生まれやすくなることから、気持ちをさらに沈ませる原因になります。
自己評価が極端に下がっているときは、産後うつの兆候かもしれません。
食欲の変化がある
食欲が急に落ちてほとんど食べられなくなったり、反対に食べ過ぎてしまうことがあります。
どちらの場合も、体重の変化や栄養不足が起こり、体調や免疫力に影響します。
授乳期は特にエネルギー消費が大きく、食事からの栄養が心と体の回復に欠かせません。
食欲の変化が長く続く場合は、心の疲れが関係している可能性があります。
自分や赤ちゃんを傷つけたい気持ちが浮かぶ
強いストレスや疲れから、自分を傷つけたい気持ちや、赤ちゃんに危害を加えてしまうのではないかという不安が浮かぶことがあります。
実際に行動するつもりがなくても、そのような考えが頭に浮かぶだけで、大きな動揺や罪悪感を伴います。
精神的に非常に辛い状態で、心身の負担も大きくなるため、出来るだけ早く専門的な支援を受けることをおすすめします。
産後うつを引き起こす主な原因

産後うつは、出産による体や心の変化、そして生活環境の大きな変化が重なって起こりやすくなります。
ここでは、産後に気持ちが不安定になりやすい主な原因を挙げ、産後うつの背景や影響について分かりやすくお伝えします。
ホルモンバランスの急激な変化
出産後、妊娠中に多く分泌されていたエストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンは、数日から数週間という短い期間で急激に減少します。
ホルモンバランスの急激な変化は、体の回復だけでなく脳や神経の働きにも影響し、気分の落ち込みや不安感を引き起こす原因となります。
ホルモンの減少はストレスへの耐性を弱め、物事を必要以上に悲観的に受け止めやすくなることもあります。
産後すぐの時期に情緒が不安定になるのは自然なことです。体の変化を知っておくことで、「自分だけがおかしいのではない」と安心して、必要なサポートを受けやすくなります。
慢性的な睡眠不足や育児疲労
赤ちゃんは昼夜を問わず数時間おきに授乳やおむつ替えが必要なため、まとまった睡眠時間を確保することが難しくなります。
睡眠不足が続くと体の疲労が蓄積し、脳も十分に休めないため、感情のコントロールがしづらくなります。
さらに、授乳や抱っこによる肩や腰の痛み、家事や他の家族の世話との両立による肉体的な負担も加わります。
慢性的な疲労は心にも影響を与え、気分の落ち込みや集中力の低下を招くことがあります。
特に「休みたいのに休めない」状態が長く続くと、産後うつのリスクが高まります。
周囲の人に協力をお願いし、短時間でも休息を取るようにしましょう。
体を横にしたり、ボーっとしたり、「自分のための時間」を数分でもよいので確保してみましょう。
周りからのサポート不足や孤立
家族やパートナー、友人からの協力が十分に得られない環境では、育児や家事を一人で抱え込んでしまうことが多くなります。
相談できる人が身近にいなかったり、気持ちを理解してもらえない状況では、孤独感や不安感が強まります。
特に初めての育児では、経験がないことへの不安から「自分はちゃんと出来ていないのでは」と自分を責めてしまうこともあります。
また、大人と会話する機会が減ることで気持ちが沈みやすくなり、ストレスも溜まりやすくなります。
周りからの孤立感は産後うつの大きな要因の一つであり、気軽に助けを求められる環境を作ることが求められます。
産後うつの気持ちを軽くするためにできること
産後の心と体は大きな変化の中にあり、無理を重ねると気持ちが疲れてしまうことがあります。
ここでは、少しずつでも心を和らげるために、日常の中で取り入れやすい工夫や過ごし方をご紹介します。
栄養・運動・休養で体調を整える
出産後の体は大きなエネルギーを使い、思っている以上に回復まで時間がかかります。
そんな時期こそ、栄養・運動・休養のバランスを意識することが大切です。
野菜や魚、肉、穀物をバランスよく取り入れ、ビタミンやミネラル、タンパク質をしっかり補うことで、体の回復と心の安定が進みます。
さらに、気分転換を兼ねて短時間の散歩や軽いストレッチを行うと、血流が良くなり気持ちも前向きになりやすくなります。
家事や授乳の合間に10分でも横になる時間を確保できれば、体力と心の両方が少しずつ元気を取り戻しやすくなるでしょう。
家族や信頼出来る人と気持ちを共有する
産後は、育児や家事、生活リズムの変化によって、気持ちが揺れやすくなる時期です。
そんな時には、一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人、パートナーに小さなことでも話してみましょう。
「こんなことで相談していいのかな」と思うようなことでも、言葉にするだけで気持ちが少し軽くなります。
相手に状況を具体的に伝えることで、サポートしてもらえる場面も増えます。
家事や育児を少しでも分担してもらえると、自分のための時間や休憩が持てて、気持ちが落ち着きやすくなります。
リラックスできる時間を意識的に作る
毎日の育児の中で、自分をリラックスさせる時間を取り入れることは、非常に大切です。
例えば、好きな音楽を流しながらお茶を飲む、香りの良いアロマを焚く、数分だけ目を閉じて深呼吸するなど、ちょっとした工夫でも気分は変わります。
特別な準備や道具は必要無く、日常の中でできる範囲で大丈夫です。
ほんの短い時間でも、自分だけの「ほっとできる瞬間」を持つことで、心に余裕が生まれ、育児への向き合い方にも少しずつ変化が出てくるはずです。
まとめ
産後は、心も体も本当に大きく変わります。
思っている以上に気持ちが揺れたり、ちょっとしたことで涙が出たり…そんな自分に戸惑う方も多いはずです。
でも、それは決して特別なことではありません。むしろ自然な変化であり、無理せず向き合っていいことなんです。
私たち特定非営利活動法人 地域母親支援サージファムは、そんなお母さんたちの“ほっとできる居場所”でありたいと願っています。
母親交流サロン「Sun-Bar」や助産師による子育て相談、産後ケアを通して、安心感と温かいつながりをお届けしています。
産後の悩みや日々の小さな不安も、一人で抱え込む必要はありません。
「眠れているのにスッキリしなくて疲れが取れないのです。」、「気が付いたらボーっとしていて誰とも話していないのです。」など、お母さん自身が「何となくおかしい」と思った時には、どうぞ気軽に、私たちのところへ遊びに来てください。
お母さんと赤ちゃんにお会いできるのを、心から楽しみにしています。