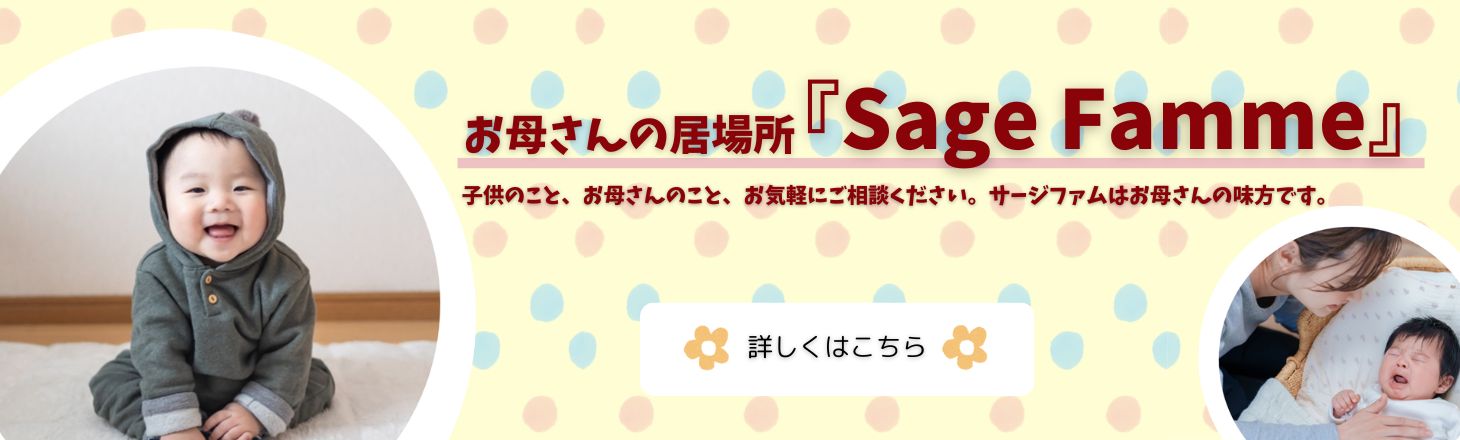高崎市の産後ケア・母親支援
お役立ち情報
赤ちゃんが夜中や明け方に何度も起きるのはなぜ?心地よく眠るコツ

-
 この記事の監修
この記事の監修
髙津 三枝子(特定非営利活動法人 地域母親支援サージファム)・助産師免許
・群馬大学大学院医学系研究科博士前期課程修了
・群馬県内看護系大学、助産師学校非常勤講師
毎日子育てに奮闘し、心身ともに疲れを感じているお母さま方を少しでもお助けしたいという想いから、
特定非営利活動法人 地域母親支援サージファムを設立いたしました。以来、皆さまの育児が少しでも楽になるよう、日々努めております。
赤ちゃんが夜中や明け方に何度も起きると、ママもなかなか眠れず、疲れがたまりやすくなります。
眠りが浅い時期や生活リズムが整っていない時期は、どうしても夜中に何度も目を覚ましてしまうことがあります。
ぐっすり眠れるようになるには、少しずつ生活リズムを整えたり、寝る前の環境を工夫したりすることが大切です。
赤ちゃんの眠りの特徴を知り、できることから無理なく取り入れていけば、夜の睡眠が少しずつ落ち着いていくこともあります。
目次
赤ちゃんが夜中や明け方に何度も起きるのはどうして?
赤ちゃんが夜中や明け方に何度も起きるのは、成長の過程でよくあることです。
昼夜のリズムが整っていなかったり、眠りが浅かったりするため、ちょっとした刺激で目を覚ましやすくなります。
不安を感じて泣くこともあるので、赤ちゃんが安心できる環境を作ることが大切です。
新生児はまだ昼夜の区別がついていない
生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ昼と夜の違いを理解していません。
大人は朝に目覚め、夜に眠る生活リズムが整っていますが、新生児はそのリズムができておらず、短い時間ごとに眠ったり起きたりを繰り返します。
赤ちゃんの眠りはとても浅く、1回の睡眠サイクルが約40〜50分と短いため、ちょっとした刺激でも目を覚ましてしまいます。
お腹が空いたり、おむつが濡れて不快に感じたりするのはもちろんですが、手足が思わぬ動きをしてびっくりする「モロー反射」で目を覚ますことがあります。
昼夜のリズムが少しずつ整い始めるのは、生後2〜3ヶ月頃からです。それまでは、夜に長く眠ることが難しく、こまめな授乳やおむつ替えが必要な時期です。
新生児が頻繁に目を覚ますのは、自然なことなので「そういう時期なんだな」と、考えて過ごすことが大切です。
成長とともに睡眠サイクルが変わる
赤ちゃんの眠り方は、成長とともに少しずつ変わっていきます。
新生児の頃は短い時間ごとに目を覚ますことが多いですが、生後3〜6ヶ月頃になると昼と夜の区別ができ始め、夜の睡眠時間が少し長くなることがあります。
ただし、別の理由で夜中に目を覚ましやすくなることもあります。
例えば、生後4〜6ヶ月頃は寝返りを覚えたり、手足を活発に動かすようになる時期です。
眠りが浅くなったときに体が動いてしまい、その動きに驚いて目を覚ましてしまうこともあります。
また、昼間に見たものや経験したことが頭の中で整理される過程で、夜中に目を覚まして泣くこともあります。
さらに、生後6ヶ月頃になると授乳の回数が減ってきます。授乳が寝る合図になっていた赤ちゃんは、新しい寝かしつけの方法を取り入れるのも効果的です。
寝るときに抱っこや授乳が習慣になっていると、習慣が無くなった途端に眠れなくなり、夜中に何度も目を覚ましてしまうことがあります。
明け方は眠りが浅くなりやすい
赤ちゃんの眠りは、朝に向かってだんだんと浅くなります。
睡眠の仕組みが関係していて、大人でも朝方になると浅い眠りが増えるのと同じです。ただし、赤ちゃんの睡眠サイクルは大人よりも短いため、明け方に目を覚ましやすくなります。
また、朝になると部屋が明るくなり始めたり、外の物音が増えたりします。赤ちゃんは環境の変化に敏感なので、ちょっとした光や音の影響を受けて起きてしまうこともあります。
さらに、お腹が空いたり、おむつが濡れていることに気づいて目を覚ますこともあります。
明け方に何度も起きてしまう場合は、遮光カーテンを使って部屋を暗くしたり、室温を調整して快適に眠れる環境を整えることが大切です。
また、夜中に目を覚ましても、すぐに抱き上げずに少し様子を見ると、自分で眠りに戻ることもあります。
夜中に起きるのは安心したい気持ちの表れ
赤ちゃんが夜中に目を覚まして泣くのは、お腹が空いているときやおむつが濡れているときだけではなく、「安心したい」という気持ちが関係していることもあります。
赤ちゃんは、大好きな人のぬくもりを感じることで安心します。夜中に目を覚ましたときにママやパパの姿が見えないと、不安になって泣いてしまうことがあります。
特に生後6〜9ヶ月頃になると、「分離不安」が強くなる時期に入ります。
昼間でもママが少し離れると泣いてしまうことが増えるのと同じように、夜も「そばにいてほしい」という気持ちから泣いてしまうのです。
夜中に泣いたときにすぐ抱っこをすると、「泣けば抱っこしてもらえる」と覚えてしまうこともあります。泣いたときはすぐに抱き上げず、少し様子を見てみるのもひとつの方法です。
また、昼間のスキンシップを増やしたり、「いないいないばあ」などの遊びを取り入れることで、赤ちゃんに「ママやパパはちゃんとそばにいるよ」と安心感を与えることができます。
赤ちゃんがぐっすり眠れるようにするには?

赤ちゃんがぐっすり眠れるようにするには、生活リズムや寝る前の環境を整えることが大切です。
朝に光を浴びたり、寝る前にゆったり過ごしたりすることで、眠りやすくなります。
また、授乳や寝かしつけの仕方を少しずつ変えると、夜中に起きる回数が減ることもあります。
朝はしっかり光を浴びて体内時計を整える
赤ちゃんが夜ぐっすり眠るためには、朝の過ごし方がとても大切です。
朝にしっかり光を浴びることで、体が「朝がきた」と感じ、夜には自然と眠くなるようになります。このリズムが整うと、夜中に何度も起きにくくなることが期待できます。
朝は、できるだけ決まった時間にカーテンを開けて、部屋に自然な光を取り入れてみましょう。
日光を浴びることで、赤ちゃんの体内で「セロトニン」というホルモンが作られ、昼間は元気に活動しやすくなります。
そして、夜になると、このセロトニンが「メラトニン」に変わり、眠りを促してくれるのです。
毎日決まった時間に朝の光を浴びることで、赤ちゃんの体内時計が少しずつ整っていきます。午前中にお散歩をするのも、リズムをつけるのに役立ちます。
眠る前の環境を整える
赤ちゃんがぐっすり眠れるようにするには、寝る前の環境を落ち着いたものにすることが大切です。
部屋が明るすぎたり、テレビの音が聞こえたりすると、赤ちゃんの脳が覚醒しやすくなり、寝つきにくくなったり、夜中に何度も目を覚ましたりすることがあります。
寝る1時間ほど前から、部屋の明かりを少し暗くして、静かで落ち着いた雰囲気を作ってみましょう。
豆電球や間接照明を使うと、やさしい光になり、赤ちゃんもリラックスしやすくなります。
また、寝る直前まで遊んでいると、気持ちが高ぶってしまい、なかなか眠れなくなることもあります。
寝る前の時間は、絵本を読んだり、静かな音楽を流したりしながら、ゆったり過ごすのがおすすめです。
お風呂のタイミングを見直してみる
お風呂には、赤ちゃんの体を温め、リラックスさせる効果があります。
ただし、入る時間が遅すぎると、体が温まりすぎて寝つきにくくなることもあります。
お風呂に入った後は、体の深い部分の温度(深部体温)が下がるときに自然と眠くなるので、寝る30分〜1時間前くらいにお風呂を済ませるのが理想的です。
お湯の温度は38〜40度くらいのぬるめがベストです。熱すぎるお湯だと体が目覚めてしまい、逆に眠りを妨げることもあります。
また、お風呂上がりに明るい部屋で過ごすと、赤ちゃんの目が冴えてしまうことがあるので、入浴後は照明を落として、落ち着いた環境を作るとよいでしょう。
授乳や寝かしつけの習慣を少しずつ見直す
夜中に何度も起きてしまう原因のひとつに、「寝るときの習慣」があります。
特に授乳をしながら寝るのが習慣になっていると、夜中に目を覚ましたときに「おっぱいがないと眠れない」と感じてしまい、何度も起きてしまうことがあります。
少しずつ授乳のタイミングを変えていくことで、赤ちゃんが授乳なしでも眠れるようになります。
例えば、寝る直前の授乳をやめて、お風呂の後や寝る前の30分に授乳をすると、「授乳=寝る時間」という習慣が和らいでいきます。
また、抱っこやトントンで寝かしつけている場合も、最初は短い時間だけ布団に寝かせてみるなど、少しずつ変えていくと、自分で眠る力が育ちやすくなります。
急にやめるのではなく、赤ちゃんの様子を見ながら、ゆっくりペースで見直していくのがポイントです。
夜中に起きたときはすぐに抱っこしなくても大丈夫
赤ちゃんが夜中に目を覚ますと、すぐに抱っこしてあやしたくなりますが、実は少し様子を見るだけで、赤ちゃんが自分でまた眠ることもあります。
寝ぼけているだけのことも多く、ちょっとぐずったり、小さな声で泣いたりするくらいなら、しばらく待ってみると自然に寝ることもあります。
すぐに抱き上げると、赤ちゃんが完全に目を覚ましてしまい、かえって眠りにつきにくくなることもあります。
眠りが浅くなってぐずっているときは、お腹や背中を軽くトントンしたり、優しく声をかけたりするだけで落ち着くこともあるので、まずはそれを試してみるとよいでしょう。
もし、赤ちゃんが大きな声で泣き続ける場合は、不安を感じていることが多いので、抱っこしてあげても大丈夫です。
大切なのは、赤ちゃんの様子を見ながら、少しずつ「自分で眠る力」を育てていくことです。
ママも無理せず、休めるときに休もう

赤ちゃんのお世話は想像以上に大変で、夜中に何度も起きるとママの疲れもたまりやすくなります。
無理をしすぎると、心も体もつらくなってしまうことも。できるだけ休める時間を見つけて、少しでも体を休めることを大切にしていきましょう。
赤ちゃんの睡眠リズムに合わせてママも休む
赤ちゃんが夜中に何度も起きると、ママの睡眠時間もどうしても短くなってしまいます。
まとまった睡眠がとれないと、疲れがたまりやすく、イライラしやすくなることもあります。赤ちゃんが寝ている時間を上手に活用し、短時間でも体を休めることが大切です。
昼間に赤ちゃんが眠ったら、家事を後回しにしてでもママも横になるだけで疲れが和らぎます。眠れなくても、目を閉じて深呼吸するだけでも気持ちが落ち着くことがあります。
すべてを完璧にこなそうとせず、「休めるときに休む」を意識することで、心にも少しゆとりが生まれます。
ひとりで頑張りすぎないことが大切
赤ちゃんのお世話をすべてひとりでこなそうとすると、心も体も疲れてしまいます。
毎日24時間気を張り続けるのはとても大変なこと。赤ちゃんが夜中に何度も起きる時期は、特に周りの人の助けを借りることが大切です。
パパや家族に赤ちゃんを見てもらう時間を作ったり、一時預かりサービスを活用するのもひとつの方法です。
少しの間でも赤ちゃんと離れる時間を作ることで、気持ちがリフレッシュし、また優しく向き合えるようになります。
ママが笑顔でいることが、赤ちゃんにとっても一番安心できる環境になります。
完璧じゃなくて大丈夫、ゆっくり向き合おう
赤ちゃんが夜中に何度も起きると、「どうして寝てくれないんだろう」「何か間違っているのかな」と不安になることもあります。
でも、赤ちゃんの眠りには個人差があり、すぐに解決できることばかりではありません。
赤ちゃんが泣いたら、少しずつ対応の仕方を変えてみたり、試行錯誤しながらママと赤ちゃんに合った方法を見つけていくことが大切です。
「今日はうまくいかなかったな」と思っても、次の日にはまた新しい方法を試してみるくらいの気持ちで大丈夫。
お母さんが休めない時は、どうしても赤ちゃんをコントロールしようとしてしまいがちです。休みたいと思うときほど、実は赤ちゃんをお母さんのリズムに無理やり合わせようとさせているかもしれません。
赤ちゃんのリズムに母さんが合わせるようにすると、泣いている声の大きさや様子で赤ちゃんが求めていることが少しずつ理解できるようになってくるものです。
焦らず、ゆっくり向き合いながら赤ちゃんの成長を見守っていきましょう。
まとめ
赤ちゃんが夜中や明け方に何度も起きるのは、成長の途中ではよくあることです。
昼と夜のリズムがまだ整っていなかったり、眠りが浅かったりすると、ちょっとした刺激で目を覚ましてしまいます。
朝の光を浴びる習慣をつけたり、寝る前の環境を整えたりすることで、少しずつ眠りのリズムが整っていきます。
ママも無理をせず、休めるときにしっかり休むことが大切です。焦らず、赤ちゃんと一緒に少しずつ心地よい眠りの習慣をつくっていきましょう。
いろいろ試しても赤ちゃんが眠らない、昼寝しないなど困ったときには、ぜひ一度サージファムにご相談ください。
赤ちゃんの発達段階、気質など、ひとりひとりに合わせた解決方法を一緒にお考えできればと思います。